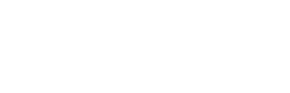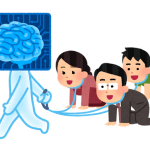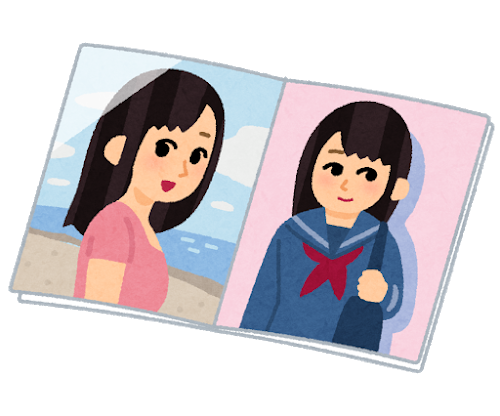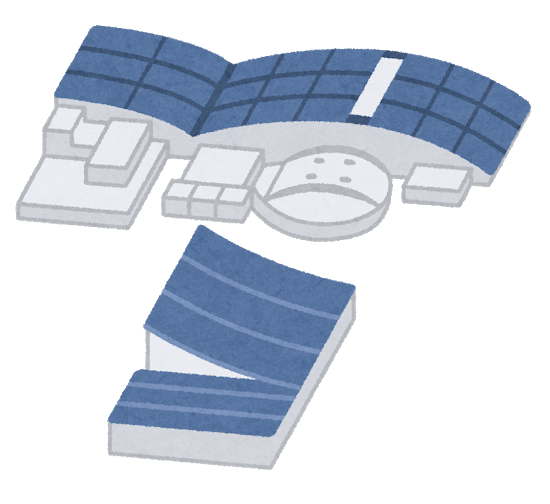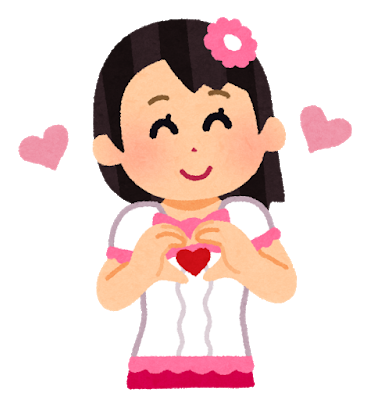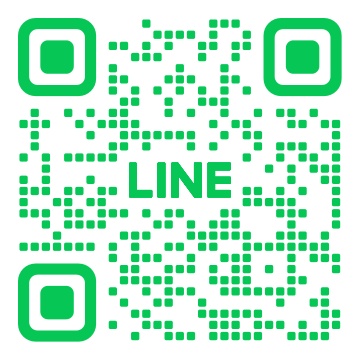ITmedia ビジネスオンラインで興味深い記事が載っていたので、紹介しておく。こういう考えも一理あると思うので。難しい時代になってきましたね。広告屋としては、クライアントは神であるけれど、世の中も空気も大切で、クリエイターは板挟みですな。
だから、なんども「炎上CM」がつくられていく
大企業や自治体のPR動画がたて続けに「女性蔑視」で炎上している。
直近でいえば、息子の誕生日だというのにまっすぐ帰宅せず、ミスをした後輩と一杯飲むという父親が、「ただただ不快でしかない」という怒りの声がわきあがった「牛乳石鹸」のWebムービーや、お色気満点の壇蜜さんが亀の頭をなでて大きくなるなどの描写が「卑猥すぎる」と批判された宮城県のPR動画「涼・宮城の夏」などが思い当たるだろうが、この1年を振り返っても、以下のようなものがある。
・2017年7月、サントリーのビール「頂」のWeb限定動画「絶頂うまい出張」→「男にとって都合のいい女」を表現していると批判される。
・2017年4月、ユニチャームのPR動画『ムーニーから、はじめて子育てするママヘ贈る歌』→「ワンオペ育児」に追われる母親の姿に、「その時間が、いつか宝物になる」という締めの言葉があることで、「ワンオペ育児を美化している」という批判が寄せられる。
・2016年9月、鹿児島県志布志市の「ふるさと納税」の寄付を呼びかけるPR動画「うな子」→黒いスクール水着姿の少女が「養って」と懇願する描写に、「援助交際」や「少女監禁」を想起させると批判される。
ここまで連発すると、「わざと炎上を狙っているのでは」とうがった見方をする方もいるかもしれないが、壇蜜さんの動画のように確信犯的に狙って仕掛けているものもある一方、つくった当事者が戸惑って、すぐに公開中止をしているケースも少なくない。「仕掛け」にしてはあまりにお粗末と言わざるを得ない。
「いやいや、そうではなく、昔と比べて社会全体が不寛容になってきているのだ」と「時代のせいだ」と考える方もいらっしゃるかもしれないが、それは気のせいだ。
「昔はもっとおおらかだった」というのはノスタルジックな幻想に過ぎず、実はこの手の「女性蔑視CM」は昔も当たり前のようにあって、当たり前のように批判を受けてきた。例えば、有名なのは、いまから42年前、「ハウスシャンメン」というラーメンのCMである。
年配の方はうっすら記憶にあるかもしれないが、お母さんらしき女性と小さな娘が踊りながら「私、つくる人」と自分たちを指差す。すると、画面が切り替わって、息子らしい男の子が、「僕、食べる人」と自らを指差すCMだ。
「牛乳石鹸」に不快さを感じる方ならばすぐに分かるだろうが、「メシをつくるのは女の仕事、それをドカッと座って食べるのが男の仕事」という旧態依然とした男女の役割を固定化させる、として女性団体が抗議をしてテレビや新聞でも取り上げられるほどの大きな議論を呼ぶ。その結果、2カ月後に放映中止に追い込まれたのだ。
●「炎上CM」が改善されなかった理由
その後も、この手の批判にさらされるCMはたびたび世間を騒がしてきた。そのたびに、海外では公共の目に触れる広告では、女性を物のように扱うことなど、性差別をしないという業界内ルールがあるから、日本もそうすべきだともっともらしい意見が出るのが、喉元過ぎればなんとやらで、ウヤムヤにされしばらくすると同じ騒動が起きる、ということの繰り返しだった。
つまり、最近やたらと目につく「炎上CM」というものは、SNSやネットPR動画という目新しいツールによるものなので、なにやら今の時代特有のものかと思われがちだが、なんのことはない40年以上前から続いている「日本の広告はジェンダーにうとい」という問題の「最新バージョン」に過ぎないのである。
ここで、ひとつ疑問が浮かぶのではないだろうか。
「炎上CM」が40年以上前から続く問題だというのなら、なぜなかなか改善できなかったのか。「私、つくる人 僕、食べる人」騒動の時代からこれだけ多くの批判にさらされているのだから、「いくらPVが欲しいからって、セクシー美女に亀の頭をなでなでさせるような描写をやめましょうね」というコンセンスが、広告やPRに携わる人たちの間にあってもおかしくないが、ああゆう動画が出たように特にそういう「縛り」はない。
なぜ日本の広告は「ジェンダー表現」を改善できないのか。個人的には日本の広告業界、さらには映像業界などメディアに携わる人々の組織が基本的に「男社会」であることが大きいと思っている。
例えば、大手広告代理店・電通の場合、2015年12月末で男性従業員が5184人に対して、女性従業員は2077人と28%しかいない。この傾向は「上」に行けば行くほど顕著となり、マネジメント職になると、男性1574人に対して、女性は139人と8%になる。相談役、顧問、執行役員となると34人の全員が男性だ。(電通統合レポート2016 より)
まるで電通を批判しているように聞こえるかもしれないが、これはなにも特別なことではなく、電通のクライアントである大企業もまったく変わらない。
東京商工リサーチによると、2017年3月に決算を行った上場企業2430社の役員の総数は2万8465人。このうち女性役員は957人で全体のわずか3.3%に過ぎない。
また、2015年に国際労働機関(ILO)が発表した「Women in Business and Management: Gaining momentum」によると、日本の女性管理職比率は11.1%で、108の国のうちのなかで97番目となっている。
●「炎上CM」が量産される背景
こういうコテコテの「男社会」で物事を決めようとなると、どうしても「おじさん」のセンスに引きずられるのは容易に想像できるだろう。それは「広告」という時代をつくりだす世界でも変わらない。
クリエティブな才能をもったおじさんたちが、「最近は共感を得られるプロモーションがきてるんですよ」とか「答えを出さず投げかけるような動画がバズるんですよ」なんてもっともらしいことをプレゼンする。それをフムフムとうなずいて聞く、決裁権を握る大企業のおじさんたちが「こっちのほうが我が社のイメージに合うんじゃないか」とゴーを出す。
こういう構造で生み出される広告やPR動画に、「女性」という視点をゴッソリ抜け落ちているのはある意味で当然ではないだろうか。
つまり、「女性蔑視」など女性を不快にさせるような描写が問題になる「炎上CM」が量産されるのは、日本の「広告」というものにイニシアチブが「おじさん」に握られていることの副作用のようなもなのだ。
なんてことを言うと、「男目線のCMばかりというが、最近は男が見ても不快に感じるものもるあるじゃないか」と反論をする方も多いかもしれない。
確かに、最近話題になったP&Gの「ファブリーズMEN」のCMなど「男性に対する性差別だ」という批判がでるものも多い。イケメン男性がエレベーターに乗っていると、そこに女性たちの大群が乗り込んできて、イケメンのにおいをクンクンとかぎまくる。そして、「汗臭っ」「なんか酸っぱい」などと言い放つ、というスメルハラスメントを想起させるCMである。
女性差別というCMが量産される一方で、このような男性をディスるようなCMもつくられる現象に釈然としない方も多いかもしれないが、筆者からすると、これこそが日本の広告が「おじさん社会」の産物だという証のような気がしている。
●日本のおじさんならではの発想
このコラムでも何度か紹介した安冨歩氏という人物がいる。住友銀行の行員から、気鋭の経済学者へと転身した後、現在は「女性装の東大教授」として注目を集め、さまざまな言論活動を展開している。
その安冨氏が「日本の男性が生きづらい理由」を『現代ビジネス』のインタビューのなかで述べているのだが、日本の「おじさん社会」の問題を端的に言いあわらしている。少し長いが引用させていただく。
『日本は戦時中の軍国主義のマインドのままで、表面だけ民主主義に変わっちゃったからね、精神は復員できていない。女は銃後、男は戦場。その証拠に、日本の社会って、基本的にホモマゾ(ホモソーシャルでマゾヒスティック)じゃない。たとえば会社組織って、おっさんが集まっていちゃいちゃしてるでしょ、昼も夜も休日も。ずっと一緒にいて、それでいて集団マゾなの。一緒に我慢しようね、みたいな。つまりは『貴様と俺とは同期の桜』っていう日本軍のモードのままなのよ。表面上は自由で豊かでも、腹の中は、いまだに戦時中なわけ。酒飲んで、一瞬だけプレッシャーを忘れて、また元のホモマゾの中に戻って、の繰り返し。だから日本人の男はこんなに生きづらい』(2016年1月28日 現代ビジネス)
CMをご覧になった方も分かると思うが、女性たちに匂いをクンクンされるイケメンは嫌がるわけでもなく、怒るわけでもなく、じっと目をつぶって耐え忍んでいる。同じく花王の「リセッシュ」のCMでも、大島優子さんに、スーツの臭さを指摘された男性はしゅんとうなだれる。
まるで「プレイ」のように見える「辱め」にもじっと我慢をする自虐的CMは、「ホモマゾ社会」ならではの発想である。
思い当たる方も多いだろうが、世のおじさんたちは、「ムラ」のなかのマイノリティである女性に対して無神経な言動を繰り返す一方で、自分がいかに家庭内で虐げられているのか、会社内で板挟みになっているのかというような「自虐ネタ」は好む。
「ウォータースタンド」のように、CMに登場する「おじさん」の多くが、お約束のように奥さんや子どもたちから疎(うと)まれる存在として描かれているのは、この「ホモマゾ気質」からなのだ。
●日本のCAの「女性しかいない問題」
CMやPR動画なんて作り手の自由な発想があってこそなんだから、そんなイチャモンをつけるのは止めろというお叱りもあるかもしれない。だが、社会的に影響力のあるテレビなどの映像作品には、やはりそれなりの責任もあるのではと思う。
例えば、海外を旅した人は気付くだろうが、海外の航空会社では男性のキャビンアテンンダント(以下、CA)も珍しくない。テロや乗客トラブルの安全管理面でも、男性のキャビンアテンダントがいたほうがいいというのは合理的な考えだ。実際、エールフランスのキャビンアテンダントは3人に1人は男性だ。
しかし、日本の航空会社の男性比率わずか数%で、女性が圧倒的に多い。日本ではなぜかCAは「女性の仕事」と目されているのだ。
これはなぜかというと、メディアが繰り返しそのようなイメージを触れ回ったからだ。
分かりやすいのが、1983年に平均視聴率20%と社会現象にまでなったドラマ『スチュワーデス物語』である。大映ドラマらしいドラマチックな展開に魅せられや子どものたちに「CA=女性の仕事」という概念が一気に刷り込まれた。
同じ年、エールフランスに日本人女性が24人採用された。当時は海外旅行ブームで、日本人の団体ツアーがこぞって欧州へ押し寄せていた。「爆買」の対応で日本の百貨店などが中国人スタッフを雇ったのとまったく同じ構造だが、なぜか日本では赤面するような「勘違い」がふれまわられていた。『「気くばり」は世界一 日本人スチュワーデス』(読売新聞1983年7月11日)
採用された24人のうちCA経験があるのはわずか2人のみで、「世界一のスチュワーデス」もへったくれもないが、なぜこういう「勘違い」が横行するのかというと、当時の「おじさん社会」で女性といえば、「お茶汲み係」であって、「日本女性=きめ細かいサービスで客をもてなす者」というガチガチの役割分担がされていたからだ。
こういう社会全体のイメージ付けが、日本のCAの「女性しかいない問題」に大きな影を落としている、というのは容易に想像できよう。
●「女性蔑視CM」を見て育った者
このコラムで何度も述べたが、テレビはもともと大衆を扇動する「情報兵器」として開発され、第二次大戦後は政治や消費など、大衆の「行動」に影響を与えるメディアとして姿を変えた。その「効果」がバカにできないのは、自殺報道をシャワーのように毎日繰り返すと、それにつられて自殺者がグンと増えるというウェルテル効果からも明らかだ。
つまり、「女性蔑視CM」を見て育った者は、同じようなハラスメント繰り返す恐れがあるのだ。
「たかがネットのPR動画でそんなに目くじらをたてなくても」と笑う人もいるだろう。だが、「たかがCMでそこまで目くじらたてなくても」と笑っていた結果が、「今」である。
そろそろハラスメントの連鎖を断ち切るため、作り手も真剣な議論をする時期にさしかかっているのではないか。
●スピン経済の歩き方:
日本ではあまり馴染みがないが、海外では政治家や企業が自分に有利な情報操作を行うことを「スピンコントロール」と呼ぶ。企業戦略には実はこの「スピン」という視点が欠かすことができない。
「情報操作」というと日本ではネガティブなイメージが強いが、ビジネスにおいて自社の商品やサービスの優位性を顧客や社会に伝えるのは当然だ。裏を返せばヒットしている商品や成功している企業は「スピン」がうまく機能をしている、と言えるのかもしれない。
そこで、本連載では私たちが普段何気なく接している経済情報、企業のプロモーション、PRにいったいどのような狙いがあり、緻密な戦略があるのかという「スピン」に迫っていきたい。
(窪田順生)